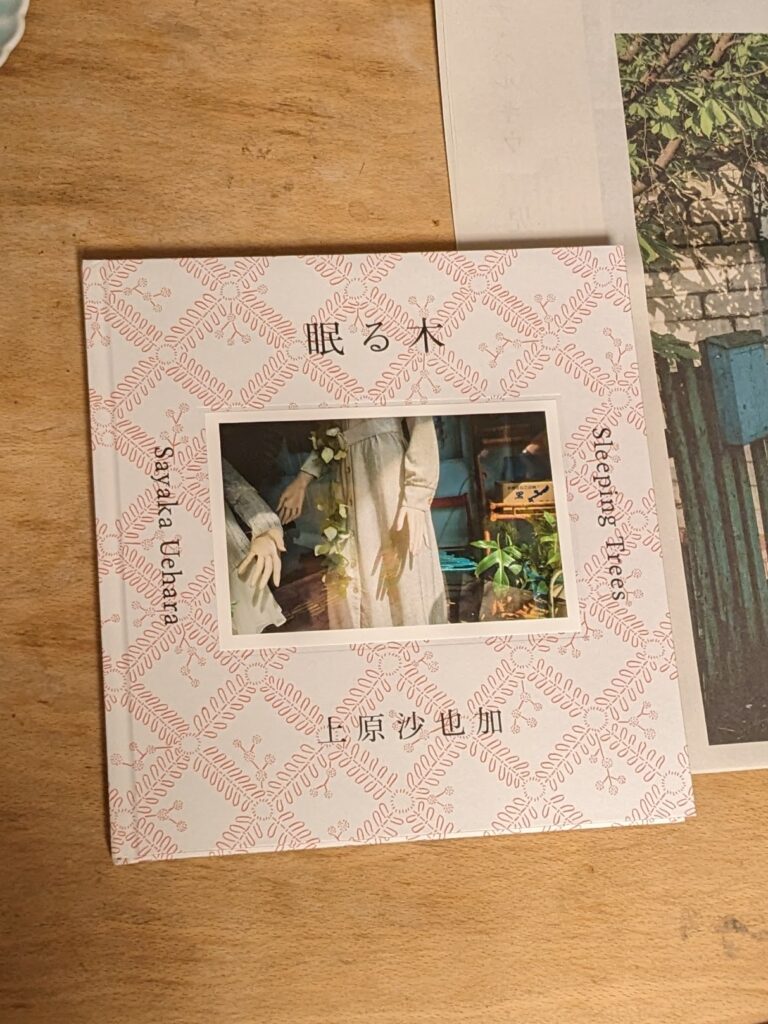岸政彦『はじめての沖縄』(よりみちパン!セ、新曜社)のカバーには3枚の写真があって三匹の猫がいる。面には2匹、袖に一匹、裏は住宅街の小道の写真。そこにも猫がいるのかもしれない。
2024−2025の年末年始、モノレールのゆいレールができてからはじめて沖縄に行った。空港直結のモノレールはとても便利。奥武山公園駅で下車し、とりあえずホテルに荷物を預け、駅までの小道に入ると低い屋根の上に猫がいた。シーサーも多いが猫も多い。
ある日、岸さんは調査のためにバスで移動する。
二月の、寒い曇りの空の日だった。いくら亜熱帯とはいえ、冬はやっぱり寒い。ー『はじめての沖縄』p150
そうなのだ。一日の気温差がすごい。私も脱いだり着込んだりした。岸さんは「いちおうガイドブックでは繁華街あるいは商店街ということになっている、近くの通り」に行く途中、一匹の痩せた野良猫を見つけ写真を撮る。それがカバーの写真というわけではないらしい。そして
(この日から毎日キャットフードを持ち歩くようになった)。ー『はじめての沖縄』p151
「いちおうガイドブックでは」というくだりも旅好きの感覚として馴染み深いし、この括弧付きもいいが、さすが猫好きさん、と思った。そしてふと思い出した。
私もいつも給食でコッペパンが出る日は放置されている犬にあげてた。今思うとあんな狭い場所に閉じ込めてひどいなと思うけど、当時はかわいいしか思っていなくて毎日寄って声をかけてちょっと遊んで(そんなスペースないからひっかけてくる前足と戯れたり)帰っていた。親が車で迎えにくるときの待ち合わせ場所もその小道の角で、大きくなってから母に「コッペパンあげてたわよね」と言われてびっくりした。私はこっそりのつもりだったが見てたのか。多分、あの犬はごはんももらってなかったんだと当時の私は知っていたのだと思う。そうじゃなきゃむやみに食べ物をあげたりしない。母も止めただろう。今はかわいそうにと思うがやっぱり当時はかわいいとしか思っていなかった気がする。かわいそう→だからコッペパン、というのは成長してからの思考回路でもっと直感的な行為だっただろう。捨て猫を拾うときだってある種の直感に突き動かされての行動だったし、いちいち理由など考えずにやっていることはとても多かったと思う。ある日、その家の表通り側に大きなゲージが出ていて中にはつかまり立ちができるくらいの小さな子がいて私と同じ学校帰りの生徒はかわいいかわいいと大騒ぎだった。私はすごく嫌な気持ちになったが、その日はその脇の狭いスペースにいるいつもの犬に会わずに表通りをそのまま帰った気がする。多分すごく怒ってた。
岸政彦さんの言葉は不思議で、書き言葉にも喋り言葉にもこういうことをたくさん思い出させる力がある。そしてこの150、151ページをめくった次のページの写真もいい。この本はページをめくっていると突然写真が登場する。特に見開きの写真はインパクトがある。目も耳も使うために足も使う。そして出会う。昔の感情とかデジャブとか一緒に歩きたかった道とか。沖縄はすでに梅雨入り。東京も今日は雨。結構降っている音がする。どうぞ足元お気をつけて。