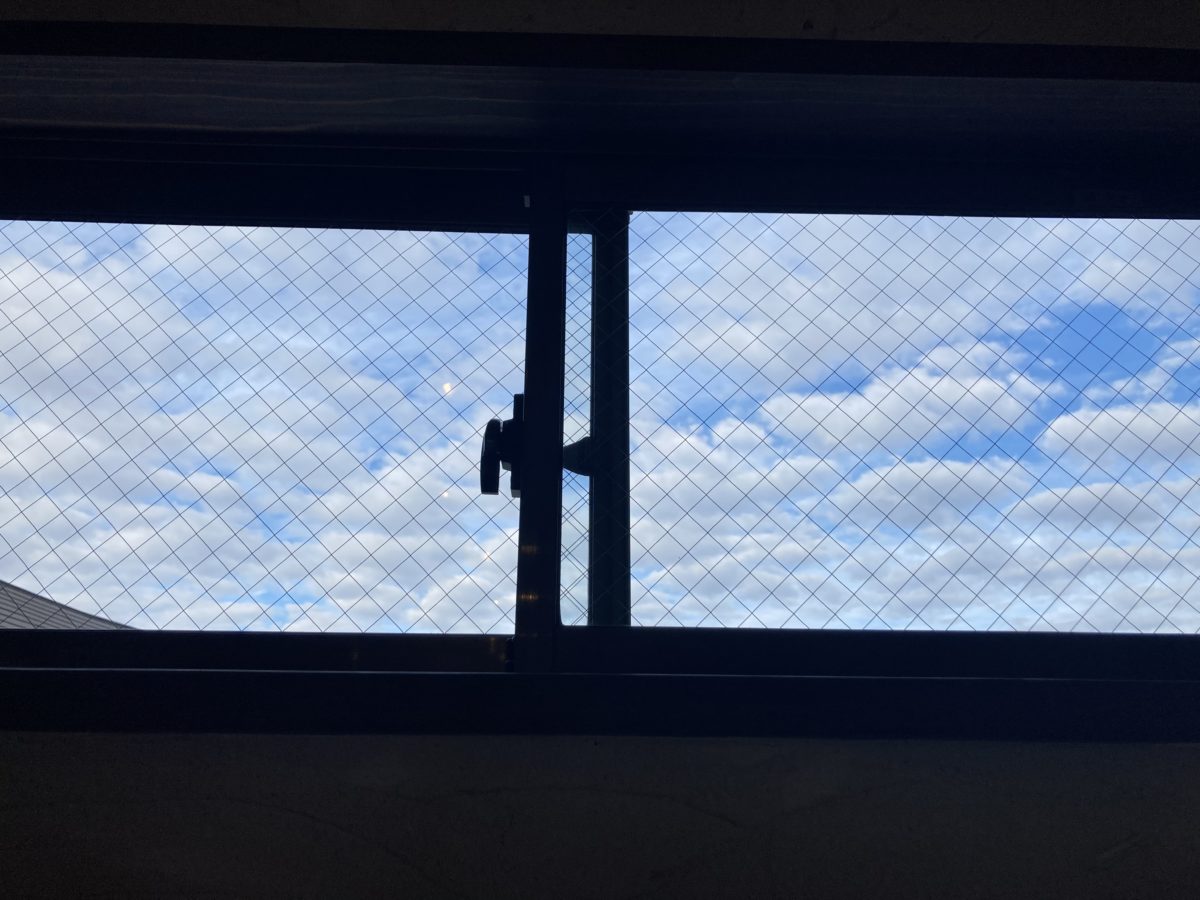相変わらず歩きながら空ばかり撮ってる。
山手線を降りて人混みを縫いながらオフィスへ向かう。新宿パークタワーの三角の屋根が空を指している。モノクロの夕暮れに向かってぼんやり歩いていると、時々後ろの人がぶつかりながら追い抜いていく。さっきよりもっと端のほうをだらだら歩く。
文化服装学院のほうに出ると道が開ける。西新宿は東や南と比べると同じような色が多いが、この辺りは華やかだ。
さっきよりモノクロの夕暮れに近づいたが、グレーの雲の濃淡ははるか彼方まで続いている。少し圧倒された。あの明るい鱗雲はどこへいってしまったのだろう。美しい水色に規則正しく並ぶ白い雲たち。立冬を過ぎた頃から感染者数が増え始めたが、その頃はまだそんな空が見られた気がする。
外灯で少し不自然に輝いている銀杏を見上げる。銀杏にも個性があって、日当たりなど環境との相互作用で色づき方は異なるという。高層ビルが好き好きな高さで建つこの街の銀杏を見ているととても納得がいく。
店の窓はクリスマスの灯りが増えた。この時期、西新宿の高層ビルにはいつの間にか大きなクリスマスツリーが現れる。オフィスを構えてからは、毎年11月に東京オペラシティのサンクンガーデンでの設営場面を見るようになった。
20年以上前、できたばかりのオペラシティを通って家に帰っていた。あの頃、一階にはドーナツ型のソファがいくつかあって、この時期になるとその真ん中にサンタクロースが置かれていた。
西新宿からも多くのベンチが撤去された。居場所を減らすことで成立する美しさとはなんだろう。
色々な色、色々な形のコートがあるものだ。まだ大きなマフラーを巻いて身をすくめるように歩いている人は少ない。上着の前も開けたまま俯き加減に、あるいは賑やかにおしゃべりをしながら女性たちが通り過ぎる。数人は新宿駅へ続く地下道へ消えていった。
まだ肩パッドが流行っていた頃の私のコートはパッドを外してもかっちりした形を保っている。これパッドの意味あったのかなと思うこともある。このコートを着ると自分のシルエットが長方形になってしまいちょっと可笑しい。背の低い私には大きすぎるような気は最初からしていた。よって着こなせず、たまにしか着なかったからまだきれいだ。でもなぜか今年はこればかり着ている。年齢がこの形に追いついてきたのかもしれない。
前方からは仕事を終えたらしきスーツ姿の男性たちが横に広がったまま向かってきた。数年前の学会で同じ学派の先生方がこんな感じで歩いてきた場面を思い出した。オーシャンズ11みたいだ、と思ったんだ、そのとき。
今年はコロナで学会なくなったけど。
道で偶然出会った年配の女性とおしゃべりをした。とても80代には思えない身のこなしで前から歩いてきた彼女にすれ違いざまに気づいた。あまり体調がよくないらしい。人を蝕むものはコロナだけではない。
お金の問題についても考えていた。オフィス街では私が一生体験することがないであろう金額の話が飛び交う。お金も人を蝕む。誰でも座れるベンチが撤去されていくように。
こころをお金で語ったのも精神分析だが、フロイトはかなり切実な問題としてこれを扱った。
精神分析家になるためには訓練が必要である。国際精神分析協会(IPA)の基準と他の団体のそれでは異なる点があるが、なんにしてもそれに「なる」ためには精神分析を受ける体験が必須だ。長い歴史に支えられた組織で長期間、ある型を自分のものになるまで身に付け、かつその少し先を見据えるために鍛錬を積む。目には見えないが手応えのある環境として、存在として、自分を提供し、かつ自分の生活を維持していくために、莫大なお金と時間をさいて修行する。提供できる自分になるために。育てる自分になるために。それは痛みにしか感じられない場合もあるけれど、もしそうならその痛みを体験する自分にじっと注意を向ける。痛みを通じて学ぶことは多い。今大人気のアニメたちもそれを描き出している。もちろんそれらが光と闇で描き出すように、痛みが憎しみに変わり奪い取ることで満足を得る自分になる可能性だってあるだろう。憎しみに覆われた彼らが空を見上げている場面はあまり見ない。
もはや運みたいなものかもしれない。精神分析家候補生になるためには訓練分析家からの査定があるが、私はそれをなんとか通過してなんとか候補生としての生活を維持している。しかし、この「なんとか」とか「ギリギリ」の感覚はいつも付き纏う。いつ終わるかわからない日々であること、大切な人をいつ失うか全くわからない日常を生きていること、その不確実さだけがなんとなく私を奮い立たせ、持ちこたえさせる。
「希望」とかたやすくいう人をわたしは疑う。というか私は言わない、たやすくは。あえてそんなこといわなくても今日もなんとかやっている、私はそういう事実を大切にしたい。そこには静かな価値が眠っている。
明日にまた会える。多分。そしたらまた写真を撮ろう。
ところで、一ヶ月前に歩きながら撮ったのはこちら。季節はめぐる。