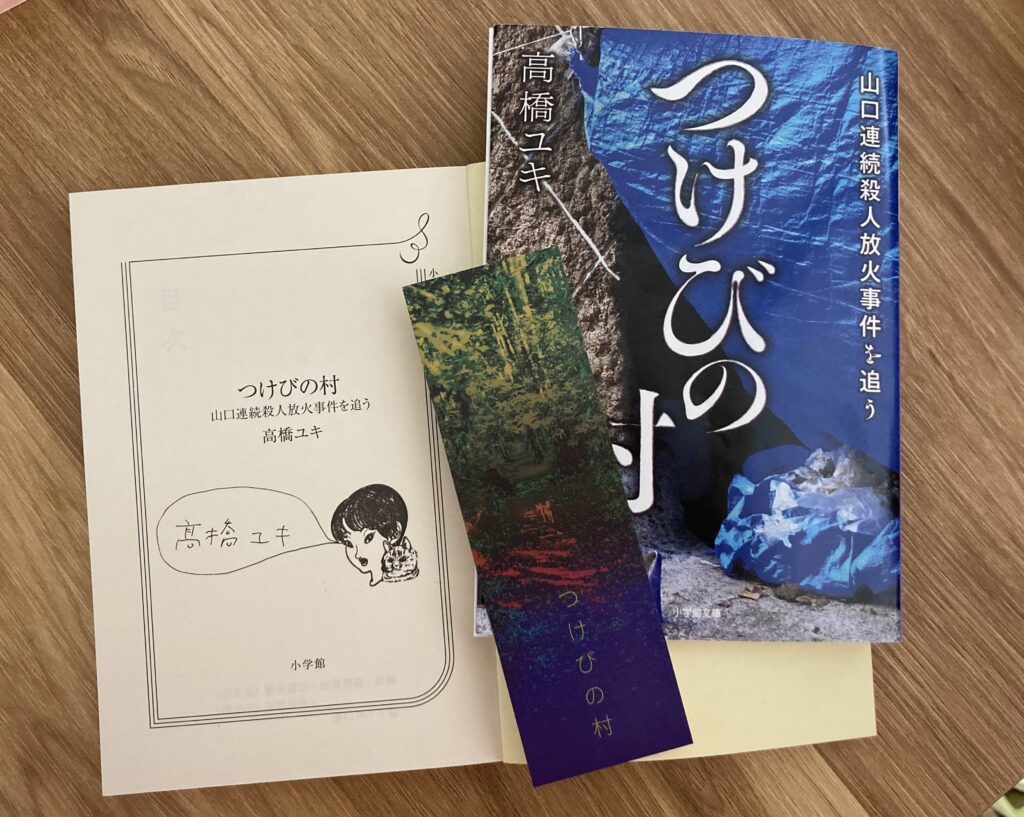おなかが気持ち悪い。おなかすいてないのに食べたのがいけない。すいてないなら食べなければいいのだけど食べないわけにもいかないのよね。食べてる間はおいしいし。あとでこうなるのもわかってるけど。
昨晩も今朝も吉田戦車の『まんが親』を読みながら時折声を出して笑っている。ほんとこどもあるあるで面白いんだけどさすが漫画家は子育てに苦労しながらも子供の言動をメモしてネタにしてるのね。面白いと思ったものを掴むのがうまいからこっちも面白いけど「え?そこ?」みたいなことを書く人がいたらいたらで面白いかもしれない。が、子供の言動こそが「え?そこ?」に満ち溢れているからどこを拾ってもあるあるとして面白いのかもしれない。大人はつまんねーな、と言ったところでおれも大人だし、というか相当大人。若くはないが私よりはずっと若いみなさんに教える立場になってからもそこそこの年数が経つが一方でまだ訓練途上でもある。分析、スーパーヴィジョン、セミナーの三本立て。そして毎月のミーティング。セミナーはもう規定時間数は修了しているが勉強に終わりなしなので今も参加することもある。先生方の教え方からも学ばないといけない。
昨晩は私が主催するReading Freudで『フロイト技法論集』(岩崎学術出版社)の「治療の開始について(精神分析技法に関するさらなる勧めⅠ)」(1913)を読んだ。先月読んだ「精神分析を実践する医師への勧め」(1912)の続きとして読める。「精神分析を実践する医師への勧め」の22−23頁でフロイトは患者に自由連想を要求する精神分析を実践する医師であるならば患者と同じように以下のような態度を維持する必要がありますよ、ということを書いている。単なる技法の羅列ではなく、これこれこうするならばこれだってそうなのだからこれこれこういうふうにすべきでしょう、みたいな書き方をフロイトはよくしていると思う。説得力がある。
「単に何か特別のことに注意を向けることなく、耳にするすべてに対して(私が以前に名付けたものと)同様の「平等に漂う注意」を維持することである。」
「すべてに等しく注意を向けるという規則が、批判や選択なく思いついたことをすべて話さなければならないという患者への要求に対する必然的な対応物であることはわかることだろう。」
「医師に対する規則は、次のように表現することができるだろう。「自分の注意能力に対してあらゆる意識的な影響を差し控え、自分の『無意識的記憶』に完全に身をゆだねるべきである」。あるいは純粋に技法的に表現するならばそれは「やるべきことはただ聞くことであり、何であれ覚えているかどうかに煩わされるべきではない。」
など。これに続いて記録をとらないことの勧めも理由つきで書かれている。そして私が最も好きな一文もそこに。
「一方、最もうまくいくのは、言ってみれば、視野に何の目的も置かずに進んでいき、そのどんな新たな展開に対しても驚きに捕まってしまうことを自分に許し、常に何の先入観ももたずに開かれたこころで向き合う症例である。分析家にとっての正しいふるまいとは、必要に応じてひとつの心的態度からもう一方の心的態度へと揺れ動き、分析中の症例については思弁や思案にふけることを避け、分析が終結した後にはじめて、得られた素材を統合的な思考過程にゆだねることにある。」
この論考の後半は分析を行なう人は自分も分析を受けるべきだということがいくつかの観点から書かれている。
「他の人に分析を行おうとする者は全員、あらかじめ自分自身が専門的知識をもつ人に分析を受けるべきである」
「自分自身のこころのなかに隠されたものを知るようになるという目的が、はるかにより素早くより少ない感情的犠牲で達成できるだけではない。書物から学んだり講義に参加したりすることでは決して得られないような印象と確信とが、自分自身とのつながりにおいて得られるのである。」
など。21頁から33頁、全部で21段落。コンパクトだ。
昨日読んだ「治療の開始について(精神分析技法に関するさらなる勧めⅠ)」(1913)は35頁から61頁、全45段落。前の「勧め」論考の2倍近く頁を割いて「さらなる勧め」をフロイトはする。
こちらは「治療の開始について」とあるように分析を実践する医師の基本的な態度というよりは初回面接や治療初期の段階における設定や患者も疑問に思うであろう事柄(お金や時間)に対する態度について詳細に書かれている。まさに今日、私がグループで中堅のみなさんと話し合う事柄だ。
そろそろNHK俳句の時間だから細かく書かないけど「まずこれ読んで」と言いたい。
それではどうぞよい一日を。