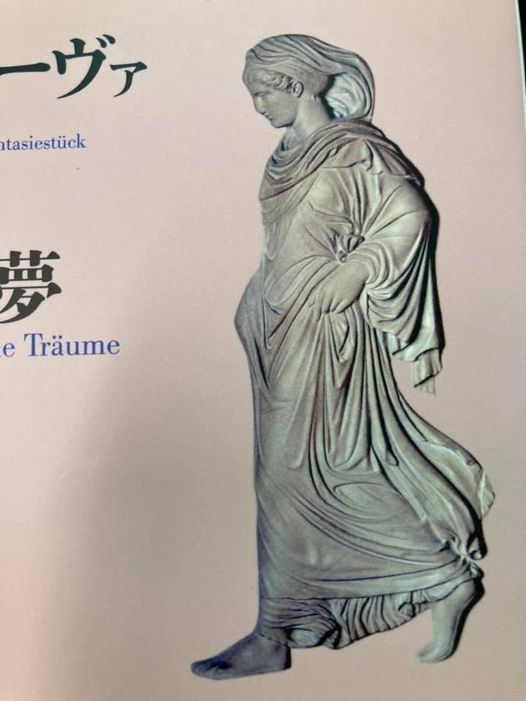8月。カレンダーをめくろう。外が白い。曇ってる。雨が降るのかな。昨日は朝は風を感じなかったけど昼間は感じた。ちょっと遠回りして久しぶりの図書館に行ったけど以前のウェルカムさは全くなく管理されている感じが居心地悪くいろんな本の背表紙だけ眺めて出た。
私は児童文学も専攻のひとつだったので図書館に行けばその棚もチェックするが、河合隼雄はそこにもいた。そもそも私が河合隼雄と出会ったのは実家の書棚にあった昔話とか子供に関する本を通じてだった。織田先生や河合俊雄先生たちに教えていただきにユング派のセミナーに出ていた頃も心理職としての河合先生が話題にあがることはあまりなかったし、実際、臨床心理士の集まりでもその場でフルートを披露された先生のことしか覚えていない。児童文化学科発達心理学専攻だった私にとって河合先生は臨床の先生というより子供のこころの先生だったらしい。精神分析を学び始めてからは精神分析は小此木先生、ユング派は河合先生という感じでその対話本などは読んでいたが、実践としてビビッドで、実際に教わりにいったのは精神分析だったら藤山先生たちの世代、ユング派だったら俊雄先生とかの世代だった。毎週木曜日、慶応心理臨床セミナーに私が通っていた頃はまだ小此木先生がいらしたので河合先生よりはずっと身近だが、精神分析かユング派かとか技法の違いでいったら、私はそのほかに家族療法も短期療法も動作法も学びに行っていたから、京大出身の仲間たちが語る河合隼雄の影響力はいまいちピンとこないし、小此木先生も特別感はない。長谷川啓三先生について名古屋に通おうとしていたし。一回だけいってすごく興味深かったけど続けたら精神分析にかけたのと同じくらいの費用がかかったかもしれない。何かのオタクになるとお金がかかる。
先生たちもそれぞれオタクだったと思う。精神分析を受ける人は少ないけどある程度オタク気質がある人たちなんだと思う。それに集中することで強いられる負担を負担と感じるしかたが独特だと思うし、精神分析はさらにメタというか、他者と共にいようとする、あるいはそこで痛みを感じる自分の心、というふうに対象が自分(=他者)になるし、自分の可動域は自分で思っているよりずっと広いか、複雑。なので痛みと不快さにまみれすごく苦しくて本当に辛くてもなんとか探求を続けられる面白さがある。私はあった。最後には「これが“遊ぶということ”か」とかなりの自由と面白さを実感できるようになったのと訓練ケースが訓練として認められたのが重なり(連動しているからだけど)分析家になる少し前に分析を終えた。今となれば何を選択しても同じ結果になったかもしれないけど、私が身をもって知っているのは精神分析だけなのでそれを生業にできてよかった。一途にオタクをやってきた。使えるものはなんでも使って、ということができる人はいいけど、私の場合は結局こんがらがって「やっぱり基礎からだな」と何度もスタート地点に戻ることになるから探求をやめないやり方が自分にあっていたんだと思う。それぞれ自分は何がしたいのか、ということに尽きるけどそれが本当にやりたいことなのかを模索するのも必要だったりするからややこしいね。
もらった温室みかんがちょうどよく甘酸っぱい。今日は金曜日。天気予報はやっぱり雨。がんばろー。