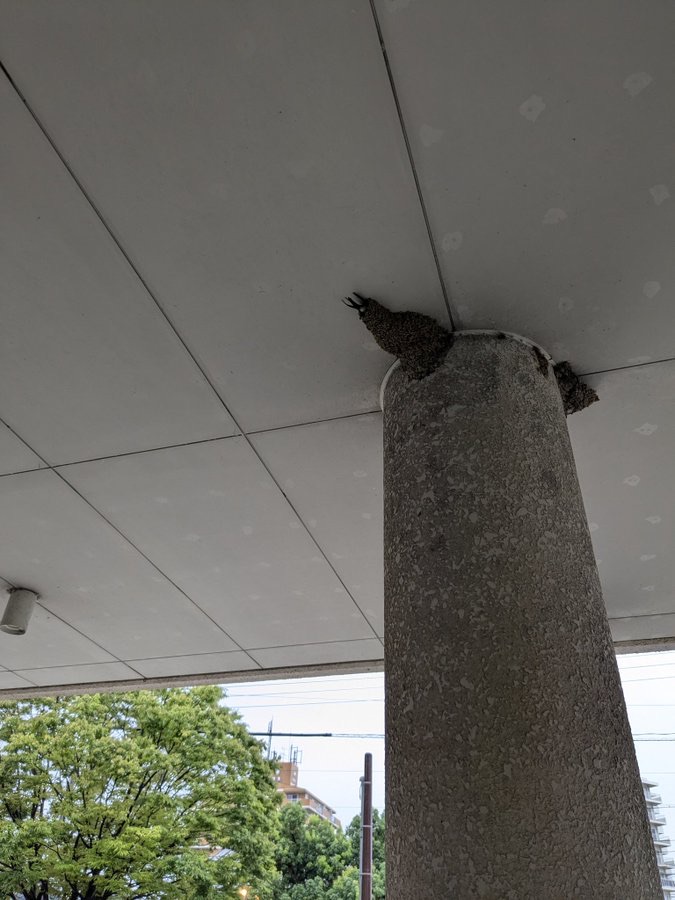毎日、空が明るくなる前に起きてしまう。そこからすぐなにかやりたいわけでもないのでカーテンの向こうに強い陽射しを感じるまでは寝ていよう、とぼんやりしていた。ウトウトしてすごく眠ったと思ったがそんなに時間は経っていなかった。そんなのを繰り返しているうちにNHK俳句の時間になったのでテレビをつけた。桃も剥いた。桃もとてもちょうどよく熟していて皮は引っ張るとつるんと向けてどろっとせずにきれいな形に切れた。果物の水分って贅沢。美味しかった。食べたらまた眠くなった。コーヒーをいれよう。寿製菓の「白ウサギフィナンシェ」をお茶菓子にしよう。有名な「因幡の白うさぎ」の洋菓子バージョン。「古事記」の神話「因幡の白兎」は有名だけど、この夏、その神様が祀られている白兎神社に行ったの。鳥取駅からバスで行けるのだけどそのバスだとその後の行程を考えたとき、白兎神社にいられる時間が短くなってしまうからちょうど出るところだった山陰本線で無人駅の末恒駅で降りて30分くらい歩いていった。おかげで結構時間が取れたし、面白い神社だった!地元の人って様子の方がひとり、またひとりと兎いっぱいの小さな神社に参拝に訪れていて、私がみたのはみなさん割と年配の男性ばかりだったのも興味深かった。
さてさて勉強のメモをしておこう。
昨晩は、Dana Birksted-Breen ”The Work of Psychoanalysis Sexuality, Time and the Psychoanalytic Mind”に収めれている6 PHALLUS, PENIS AND MENTAL SPACEを読んだ。少し前に準備したのですっかり忘れていたがみんなと話しているうちにDanaはこういうことを言いたいのだろうと考えていたことが口から出た。思い出せなくても話しているうちに出てきてそうそうそうだったとなることは多い。この人の論文は膨大な理論的裏付けがあるので、それらの歴史的変遷をこちらが踏まえている必要がある。勉強勉強。
が、今の頭の中はオグデンとそれにヒントをもらいつつ深めるウィニコット。特にウィニコットのgoing on beingについて。これは胎児の状態といえるが、ウィニコットは生まれてまもなくの状態もその延長と考えているのだろう。ウィニコットはこの特別な時期における母親と胎児の体験を彼らの時間感覚で書いているのだと思う。
オグデンThomas H. Ogdenは、サンフランシスコで開業している精神分析家。今のところ、彼の一番新しい著書、What Alive Meansもだいぶ読み進めた。次回、アプライしたい演題に向けて再読したのは7 Transformations at the dawn of verbal language。オグデンがこの章の後半で引用するヘレン・ケラーのThe Story of My Life(1903)はヘレンがサリヴァン先生との間で、前言語的な記号の世界から言語的に象徴化された世界に開かれるプロセスを描いている。言葉によってヘレンの時間がそれまでとは異なる感覚で大きく動き出す瞬間ともいえるだろう。書いてあるのはこんな感じ。
With the acquisition of verbally symbolic language, there developed a new way of experiencing, a new way of coming into being, and a new way of being alive. Emotions that she had not previously been able to feel-repentance and sorrow and love-Helen became able to experience. It is not that these feelings were latent and were waiting to be unearthed. This is emphatically not the case.
These feelings were created for the first time when Keller entered the world of experience verbally symbolized. “Everything had a name, and each name gave birth to a new thought… every object which I touched seemed to quiver with life.” Names are not simply designations for feelings and things, they are ideas about feelings and people and things. Language gives rise to a qualitatively different realm of experience, a realm in which one is both subject and object, one is able to think of oneself thinking, one is alive to levels of meaning, range of emotion, complexity of feeling, and forms of experiencing not previously attainable.
「言語的な象徴言語(verbally symbolic language)を獲得することで、まったく新しい経験の仕方、新しい存在の仕方、そして新しい生のあり方が生まれた。ヘレンは、それまで感じることができなかった感情――悔恨、悲しみ、愛――をはじめて経験できるようになったのである。だが、これらの感情がもともと心の奥に潜んでいて、掘り起こされるのを待っていたわけではない。断じてそうではない。これらの感情は、ケラーが言語によって象徴化された経験の世界に足を踏み入れたとき、初めて創造されたのである。「すべての物には名前があり、それぞれの名前が新しい思考を生み出した……私が触れたすべての物が、生命の震えを帯びているように見えた」。名前は、単に感情や物のラベルではない。それは感情や人や物についての思考そのものである。言語は、質的に異なる経験の領域を生み出す。その領域では、人は主体であり対象であり、自分自身を考えることができる存在であり、意味のレベル、感情の幅、感情の複雑さ、そしてこれまで到達できなかった経験の形態を生きることができる。」
直訳だけど。
この記述の前にオグデンの分析的第三者の記述があって、病理的な分析的第三者Pathological forms of the analytic third (“the subjugating third” (Ogden, 1996))が出てくるのだけどここは保留。the analytic thirdってこういう形態変化するものではなくてもっとニュートラルな概念として登場したのではなかったっけ、と思ったから。あとで確認。