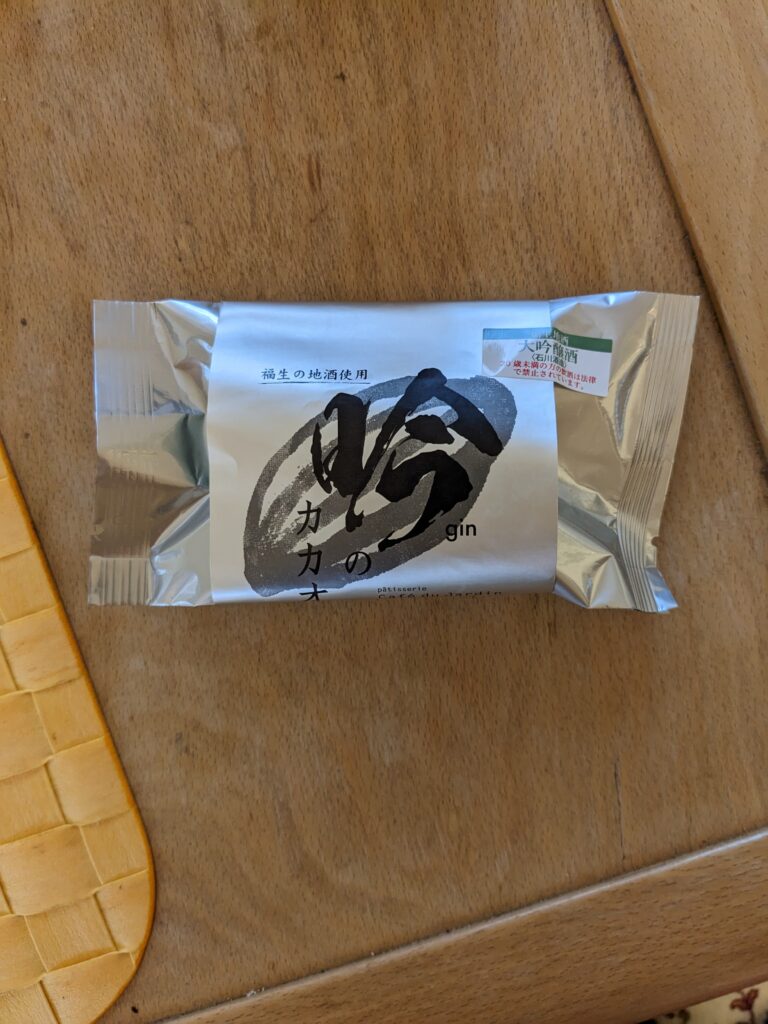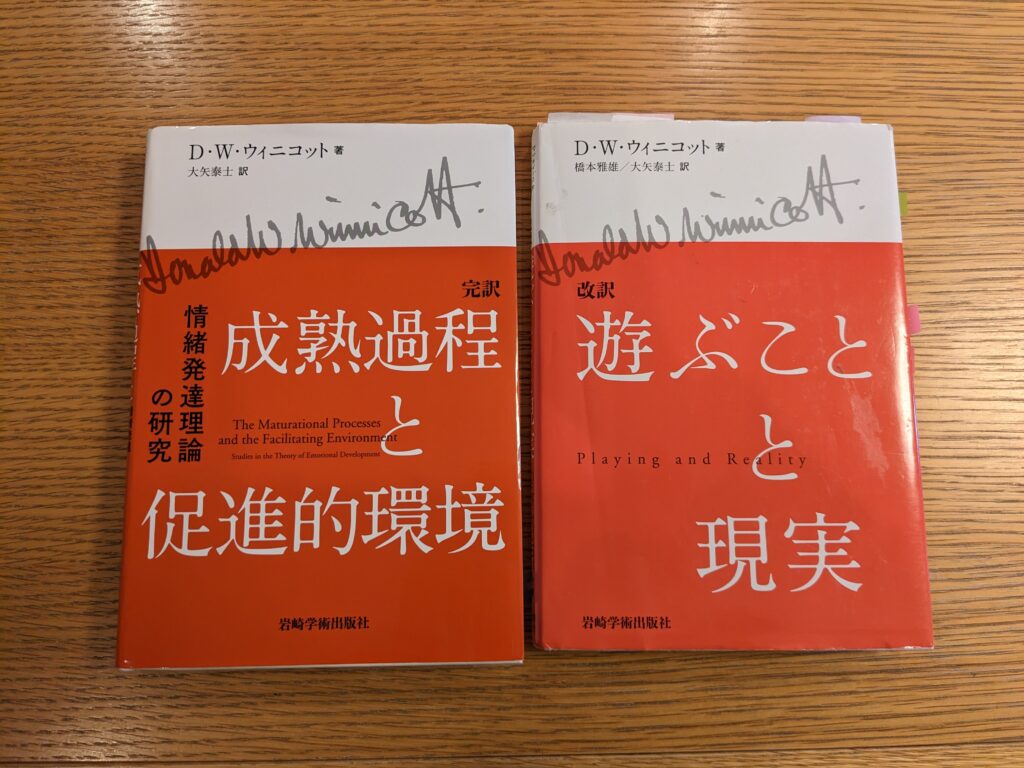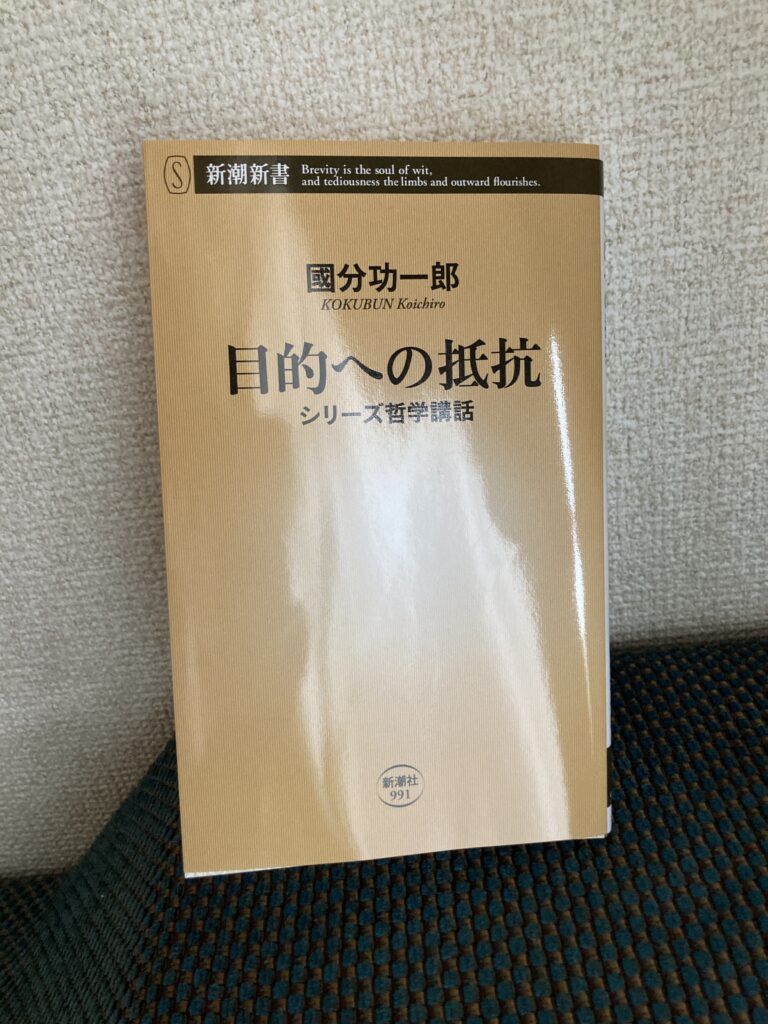昨晩は大正ロマン関連を色々チェック。旅に出るから。袴で街をそぞろ歩きしたい。今朝は吉田戦車『伝染るんです。』をパラパラ。少しずつ積み上げられた本と論文の整理をせねばと単に別の場所に移動させるようなことをしているときに見つけてしまった。ちっこい文庫。『はいからさんが通る』ではなくこっちを見つけてしまった。これ帯もつけっぱなしにしてたんだ。1巻「読んだらキケン!』2巻『不条理来襲』3巻『枠組み破壊』4巻『爆発的伝染力』5巻『非常識の完結』。『伝染るんです。』なんだから4巻のはどうかな。まあ大きなお世話かな。今こんなことしてる場合じゃいないんだよー(泣)。でも面白いよー。それにしても部屋がひどいことになっている。
Reading Freudも事例検討グループも始まったからインプットを増やしていかないとなのに別のことばかり調べてしまう。英語論文とか最近ちょっとしか読んでないからめちゃくちゃ読むの遅くなってるし。そんな賢いわけではないのだから真面目にやらないとなのにね。あー、吉田戦車とか大和和紀天才。フロイトと同じくらい読むべきものたちと思う。
一応、私が読書会でいつも言っているフロイトの書き方に意識を向けることについて話すためにオグデンの2002年の論文を再読したのであげておこう。これはオグデンの単著に入っていただろうか。訳されていないけど誰かが編集している本に入っていることは知っているけど書名を忘れてしまった。漫画読んでないでこちらをチェックしないとね。
Ogden, T. H. (2002) A New Reading of the Origins of Object-Relations Theory. International Journal of Psychoanalysis 83:767-782
The author presents a reading of Freud’s ‘Mourning and melancholia’ ということでフロイト全集14の『喪とメランコリー』をオグデンが再読。この論文は対象関係論のはじまりと言われている論文。これは十川幸司訳の『メタサイコロジー論』にも収録されているからそっちで読むといいかも。フロイトが短期間で一気に書き上げたというメタサイコロジー論文の中でも最重要。
オグデンが重要と考えるのはvoice。太字は私が太くしました。
the way he was thinking/writing in this watershed paper.
オグデンはのちに‘object-relations theory’(対象関係論)と呼ばれる心の改訂モデルの背景にあるフロイトの考えを以下に要約。
(1) the idea that the unconscious is organised to a significant degree around stable internal object relations between paired split-off parts of the ego
(2) the notion that psychic pain may be defended against by means of the replacement of an external object relationship by an unconscious, fantasied internal object relationship
(3) the idea that pathological bonds of love mixed with hate are among the strongest ties that bind internal objects to one another in a state of mutual captivity
(4) the notion that the psychopathology of internal object relations often involves the use of omnipotent thinking to a degree that cuts off the dialogue between the unconscious internal object world and the world of actual experience with real external objects
(5) the idea that ambivalence in relations between unconscious internal objects involves not only the conflict of love and hate, but also the conflict between the wish to continue to be alive in one’s object relationships and the wish to be at one with one’s dead internal objects.
要約だけだとまあそれもそうかという感じかも。症例の話がないとということで興味のある方は本文も読んでみてください。
ちなみにオグデンは下に書くフロイトの論文の終わりの部分を引用して患者の実際の生活に根ざしていないと精神分析もthe self-imprisoned melancholic who survives in a timeless, deathless (and yet deadened and deadening) internal object worldと変わらないよ、ということでこの論文を閉じています。
Freud closes the paper with a voice of genuine humility, breaking off his enquiry mid-thought:
—But here once again, it will be well to call a halt and to postpone any further explanation of mania … As we already know, the interdependence of the complicated problems of the mind forces us to break off every enquiry it is completed—till the outcome of some other enquiry can come to its assistance .
オグデンは少しだけ省略してしまっているので十川訳の方からこの部分を引用しておきます。
「しかし、ここでは再び立ち止まり、まずは身体的苦痛、それからその苦痛と類似した心的な苦痛の持つ経済論的な性質への新たな理解が得られるまで、マニーについてのさらなる解明は延期するのが適切だろう。周知のように、錯綜した心的な問題は相互に関連しているため、他の研究成果を役立てられるようになるまで、このような研究は不完全なまま中断せざるをえないのである。」
これぞフロイトの書き方という感じがする。フロイトには常に次へ継続するための中断がある。実際、ここに書かれたことは継続的に探究され別の論文に書かれています。フロイトを読み始めるとこうやって読み続けることが必要になってしまうことをみんな無意識的に知っていて敬遠してしまうのかな。ここに書いてあることがよく掴めなくてもまた出てくるから大丈夫、ということを私はよく言うけど。精神分析みたいな心の探求は時間がかかってしまうのですよ、反復につぐ反復を扱うから。まずは反復を認識するところから時間がかかるし。うーん。体験と結びつくと多分かなり読みやすくなるのだけど読むために体験するわけではないしね。精神分析を体験するのはフロイト全集を買うよりもお金もかかるしそう簡単におすすめできるものでもないし。うーん。悩ましいですね。とりあえず読んでいきましょう。