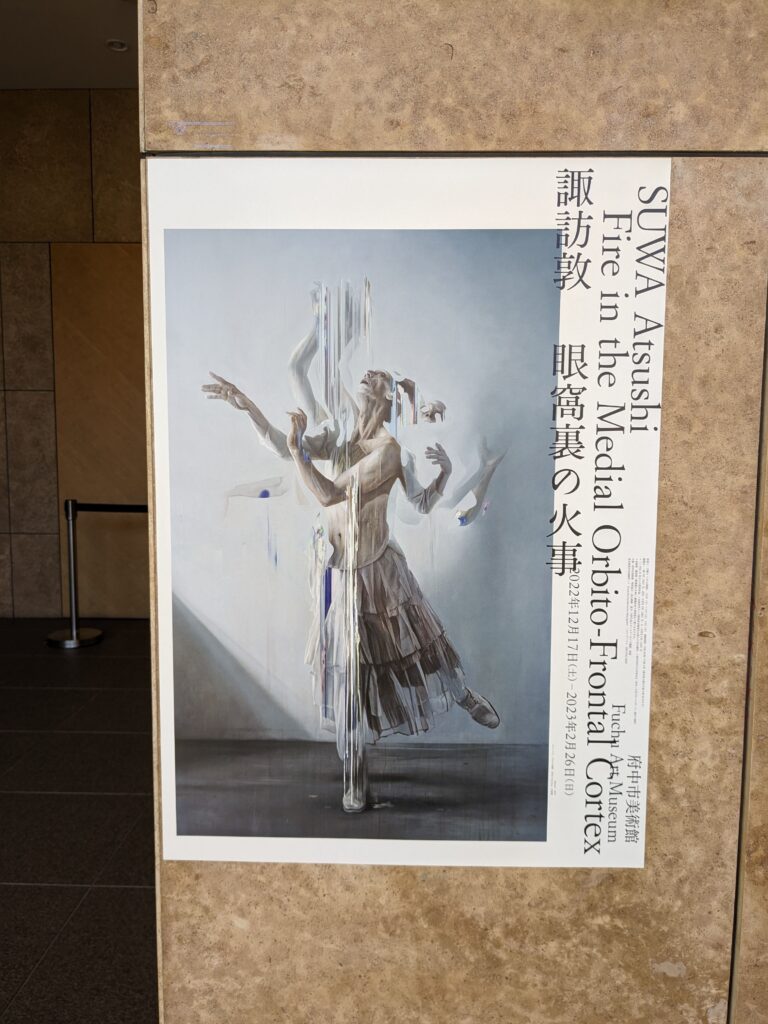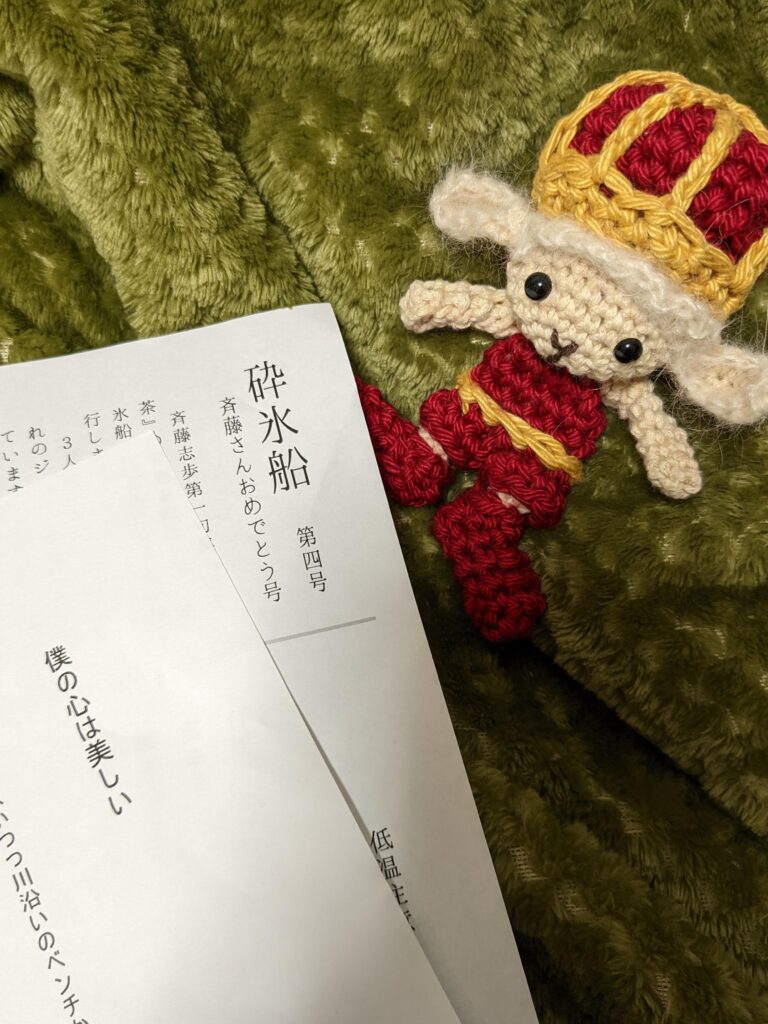細身の背の高い若い男性が子供の笑顔のまま踊るように大きく回った。同時にやはり華奢で背の高い無邪気そうな若い女性が嬉しそうに大きくスカートを翻した。さらに地べたに座りこんでいた芸術家が描いていた垂れ幕がパタパタパタと波打った。電車が通り過ぎたのだ。この貧しい街の駅には決して停まることのない特急が。もちろん舞台に電車はやってこない。音と光と彼らの動きが特急が通り過ぎたことをvividに表現していた。人間の身体はすごい。
やや冗長で噛み合わないはじまりをみせた舞台は主演の登場を得てこれから起こる不穏な出来事へと緊張感を増していく。誰も止めていない。しかし視線に囲まれている。自分が動けば引き止められる。自分はここから逃れることはできない。目の前にようやく止まった各駅停車に乗り込むことがどうしてもできない。混乱し絶望に支配されていく様子を相島一之が巧みに演じていた。
大学生の頃、重度の自閉症の青年たちが暮らす施設へ出かけて週末を共に過ごしていた。ある男性は次の一歩を踏み出すまでに何十分もかかった。彼らは大きな声を出したり楽しそうな音を出しながら笑うことはあっても言葉はでなかった。突然顔を近づけてきて手をひらひらさせながら何度も私にぶつかりそうになるくらいの距離まで頭を前後に揺らす間、彼は私をじっと見ていたけれどそれは私を通り抜けて背後に向かうような視線で私に何かを見出そうとする目ではなかった。数年間、彼らと時間を共にし、さまざまな場所に出かける中で私は彼らと随分馴染んでいた。彼らには彼らのペースと決まりがあった。それらは私たちにも多かれ少なかれあるけれど。私はいつも通り静かにそばにいて、彼は大きな身体を小さく何十回か前後に揺らしたあと一歩を踏み出し一緒にお散歩に出かけた。音、光、場所、差異に敏感な彼らにとってこの世界はとても住みにくいだろう。元気だろうか。私たちは同年代だったから彼らももうおじさんだ(男性ばかりだった)。ご家族はご健在だろうか。みなさん、元気でいてほしい。
どうしても電車に乗り込むことができない。誰も引き止めてなどいないのに。そこに視線があるだけで。カフカだ、と思った。この戯曲はスイスの劇作家、フリードリッヒ・デュレンマットの『貴婦人の来訪』であってカフカの『掟の門』ではない。これは人間が持つ普遍的な心性なのだろう。苦しい。あなたをそこに押しとどめ、進むこともひくこともできないままそこで死ぬように仕向けているのは一体誰なのだろう。
そういえば、昨年8月、最終回を迎えた吉川浩満さんのscripta (紀伊国屋書店、電子版あり)での連載『哲学の門前』がこの8月、単行本になって登場するそうだ。日常的に「掟の門」性と付き合い続け思索を重ねてきた著者がひとりのモデルとしてその付き合い方の断片を見せてくれたこの連載がさらに多くの読者を得てそれぞれが門前で死ぬことなく生きるすべを見いだせたらいいと思う。どうにかして生き残ろう、みんなで。
デュレンマットの戯曲における主人公は「逃げろ」と言われてもそうすることができなかった。誰も引き止めていないのに、身体的には。私たちを捉えるのは実際の腕だけではない。言葉、過去、思い込み、誰かを思う気持ち、あらゆる出来事から私たちは自由ではない。街の住民の貧困は彼の命と引き換えに救済された。しかしそれは果たして生きている、豊かになったといえるだろうか。
たくさんの人がでてくるこの舞台、どの人物の造形も見事だった。殺人がサイコパスによってではなく葛藤できるはずのひとりひとりの個人の集団心性に基づく狂気によって行われるとき、それは決して他人事ではないという気持ちにさせられる。私は終始、共感ゆえに舞台上の人物たちに嫌悪感を感じていた。愛が裏切られたゆえに苦しみ続け富の力で復讐を実行しようとする今や老齢の女性を演じた秋山菜津子はいつものことだが素晴らしかった。悲しみ、切なさ、かつて愛した男の棺を慈しむように抱く姿には心揺さぶられた。後半は終始涙ぐんでいた。
制作に知り合いがいる、しかもオフィスからお財布ひとつで仕事の合間に行けるという理由でいったので後から知ったのだが『貴婦人の来訪』は「新国立劇場 演劇 2021 / 2022シーズン」のシリーズ「声 議論, 正論, 極論, 批判, 対話…の物語」のひとつとして上演されたものだった。それに関する対談記事も観劇のあとに読んだ。
「正論」、患者からもよく聞く言葉だ。それって何、だから何、「正しさ」って何?私たちがもっとも囚われやすいそれに今日も私自身、惑わされるだろう。私が感じていること、考えていること、伝えたいこと、どれもこれも間違っているのではないだろうか、こんなことを言ったら嫌われてしまうのではないだろうか、たとえそれが「正論」でもそれは防衛であり攻撃である可能性を含むだろう、だから怖い。伝えればまた心閉ざされてしまうかもしれない。触れ得ない関係になるかもしれない。
コーヒーをこぼしてしまった。ほとんど飲み終わっていたが私は数cm分飲み残してしまう癖がある。PCはスタンドに立てていたので濡れたのはテーブルだけで済んだ。よかった。早速心が揺れたのだろう。すぐにこんなになってしまうのだから困ったものだ。少し敏感になっているのかもしれない。不安が強まっているのかもしれない。気をつけて過ごそう。すぐに忘れてしまうだろうけど。これまでもこれでやってきたのだからなんとかなるだろうとも思う。
こぼしたせいかコーヒーのいい香りが再び広がっている。なんだかなぁ・・・。今日からまた新しい一週間だ。週末の様子は月曜日の様子でわかると保育士の先生たちが言っていた。家族と過ごした時間が小さな彼らにとってどんなものだったか思いを馳せながらいつも通りの保育をする先生方を思い浮かべる。私もなんとかいつも通りやれたらいい。みんなもなんとかそれぞれのペースで、あまり掟や決まりにこだわらず縛られず過ごせたら。大きな地震があった地域の方もどうぞお気をつけて。