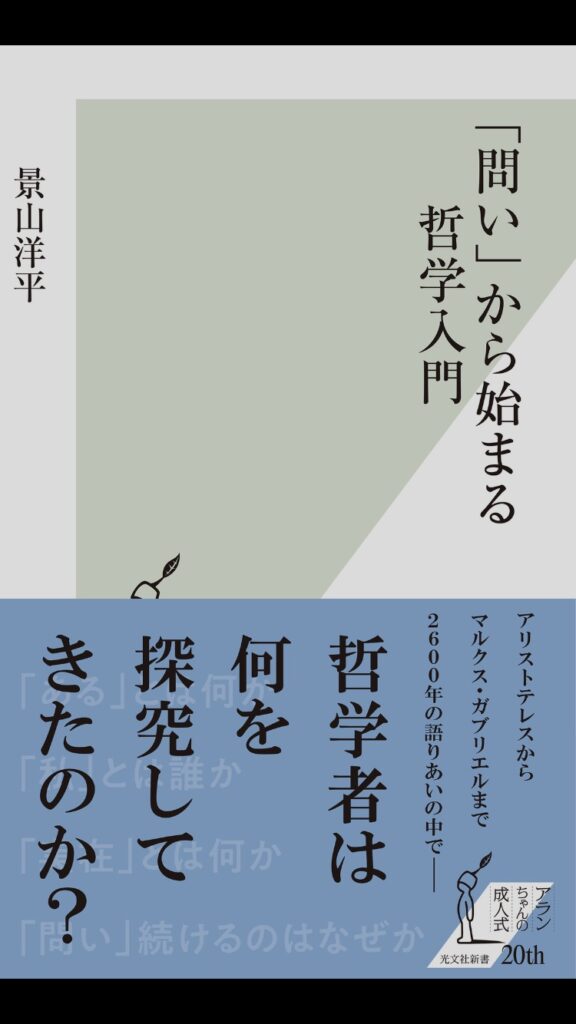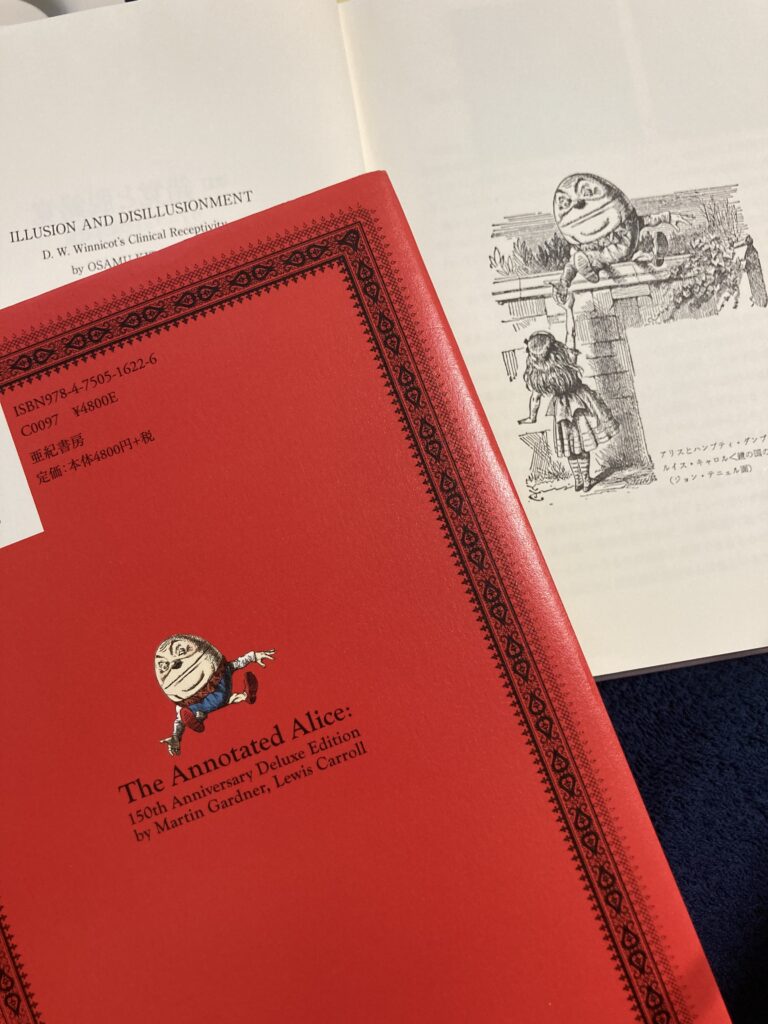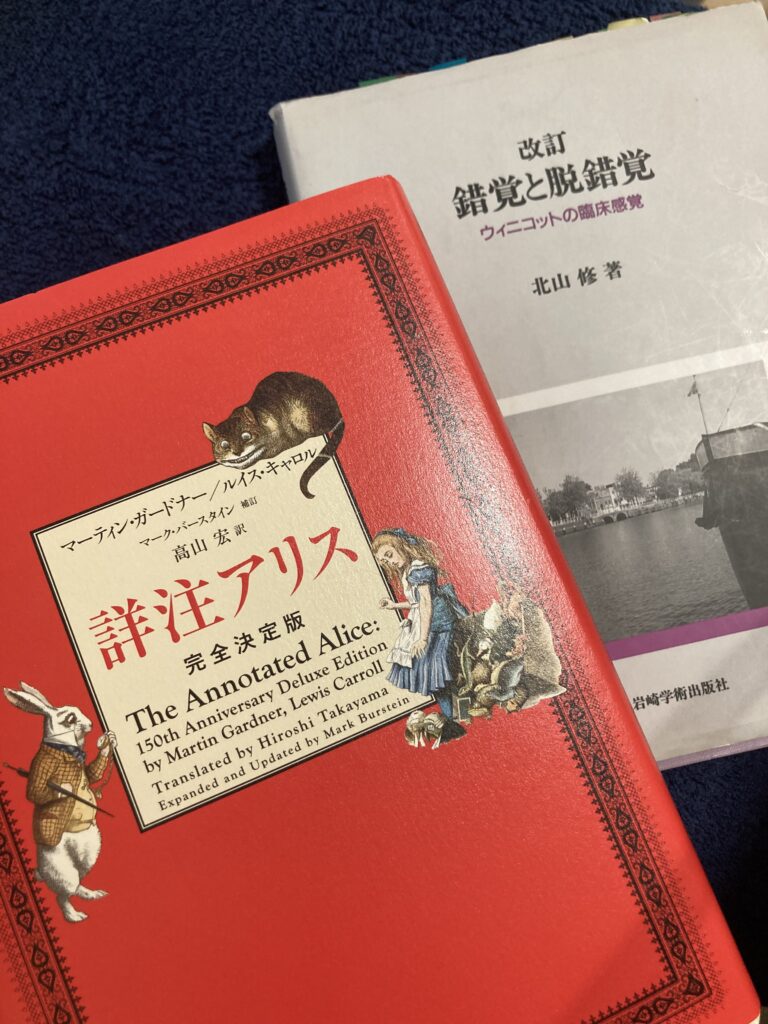今日も雨。昨晩帰宅する時間には小雨だったけどまた本格的に降っていそう。寒いし。寒さをもっと強く意識してしまう前に早朝から諸々済ませた。
7日(日)夜は「グリーフと哲学の夜 傷は癒えるのか、癒されるのか、癒すのか 」という國分功一郎さんゲストのイベントへ行ってきた。國分功一郎weekひと区切り。主催は「グリ哲2023プロジェクト」ということで袰岩奈々さん、森幸子さんを中心に普段から何か一緒に活動されているグループの企画という印象だったけど詳細はわからない。東北、関西、九州からこのためにいらした方々もあって同窓会的雰囲気もあった。お隣は関西の読書会グループの皆さんだったらしく國分さんの本はこれよりこれがいいなどなどとても盛り上がっていらした。みんなすごく楽しみにしていたみたい。もちろん私も。場所は国分寺のカフェスロー。昨年、川柳の暮田真名さんたちのイベントをしたカフェかと思っていたら違った。あちらは反対側の出口の胡桃堂。中央線は三鷹までしか馴染みがないからたまにいくと駅の中からキョロキョロしっぱなし。胡桃堂にいくのも迷ったけど駅の反対側のカフェスローにいくのも迷った。1、2分は結構自信満々に迷った。でもここを渡ったら変わるはずの町名が変わらない。迷うのもいつものことだから「こっちのはず」という予測ではなく「迷うはず」という予測に基づいてすぐ引き返した。予測モデルの話が今回ありました。熊谷晋一郎の当事者研究を参照したお話が多かったからね。さて、19時開演、18時半開場の予定が18時開場に早まったにも関わらず18時半少し前に無事に到着したときにはすでにたくさんの人がワイワイガヤガヤ。手作りイベント感があってよかった。私より年上の皆さんが多かったように見えた。質問もその場で紙に書いて集める形式だったけどたくさん出ていたし、國分さんが答えるというよりは考えこむ國分さんと一緒にみんな考えこんでまた書くみたいな感じもよかった。記憶と感情の話をするときに國分さんはフロイトの快原理を引用していた。國分さんと千葉雅也さんは精神分析理論を十分に咀嚼している哲学者なので聞きやすいし考えやすいのだけど哲学者はここでこうやってこれを持ち出すのかとかは新鮮だった。傷と痛みについて考え言葉にすること自体にどうしても攻撃性が含まれやすいことに國分さんがとても自覚的で慎重だったのも印象的だった。「サリエンシー」を導入の用語としながらそれの使えなさ、使用の難しさについて開かれていくプロセスも興味深かった。ちなみに熊谷晋一郎さんはもう「サリエンシー」という言葉は使っておらずどんどん考えも言葉も進化させているとのこと。お二人の『責任の生成 中動態と当事者研究』(新曜社)は必読でこうして痛みを伴いながら考えることをさせてくれる本だった。言葉にできない重苦しいような息苦しいような感覚が自然に大切にされる双方向的で対話的な時間は貴重。帰り道、そばを歩いていた人たちの会話が聞こえてきたがそれぞれに國分さんを通じてじっと考えさせられた様子で共感した。とても久しぶりに國分さんとお話できたしなんだか安心した。
さてさて今朝も木曽路の和菓子が甘さ控えめでおいしいです。熱いお茶と一緒に。みなさんも体調崩さないようにお気をつけてお過ごしください。

国分寺駅南口