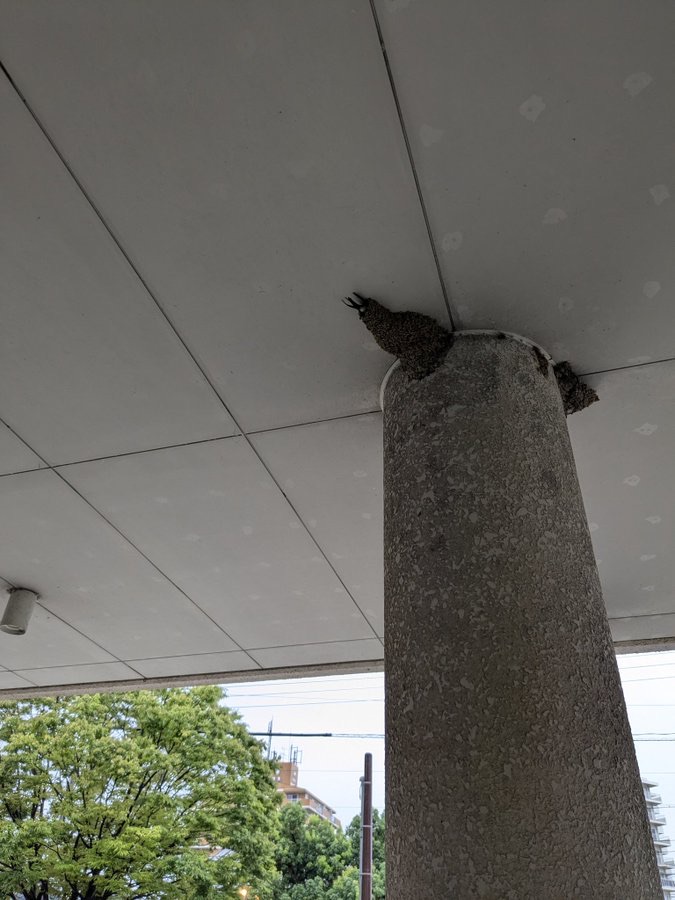1月5日(月)。まだ真っ暗です。仕事はじめ。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年も精神分析の古典を大切に、一番新しいジャーナルをウィニコット、オグデン、グリーンの考えを軸に拾い読みしつつ、隙間時間は小説や哲学の本を楽しんでいくことになると思います。読書と運動はどんな短時間でもできるのがいいですね。睡眠もほんの少し寝る、ということができるけど寝入りも寝起きも自分でコントロールするのが少し難しいです。食べるのも欲を抑えるのが本当に大変。今朝のお菓子は所沢の「お菓子の工房エミール」さんの狭山ケーキ。抹茶色のレーズンがはいった小さな焼き菓子です。おいしそう。年末にもらったルピシアの「福づくし」から今日は抹茶黒豆玄米茶と一緒に。あ、両方、抹茶になっちゃった。おいしいに違いないからいいか。うん、おいしい。所沢は昔友達の家にいったことがあるけどそれから下りたことあったっけ、と何度か思ったことあるから多分あるんだと思う。東所沢は角川武蔵野ミュージアムにいくので降りたことがある。あそこ楽しい。今年もいろんな街を歩いたり、いろんなお菓子屋さんを知りたいな。お正月明けはいろんな土地のお菓子が集まるのも楽しみ。
年末年始は徳島県にいたのだけど徳島駅から歩いて10分ちょっとかな、眉山のロープウェー乗り場(阿波おどり会館内)のそばの寺町の一角にある「和田の屋」さんの「滝の焼餅」がとてもおいしかった。お部屋も素敵だった。赤ちゃんや小さい子を連れたご家族は大変そうで思春期の子と母の二人組はとても静かで子供はずっと本を読んでいた。なんの本かなあ、と思った。お母さんがおじいちゃんと話しはじめるとお母さんを小さな手でバンバン叩いて振り向かせようとしていた子は焼き餅はあまり好みではなかったみたいだけど「すぐにこられる場所じゃないんだよ」といわれていてむしろ私が「ほんとそうだな」と思った。大切に味わった。おいしかった!その子もあれこれお母さんの関心を向けつつ食べさせてもらったらおいしそうに全部食べていたからおいしさとは、と思った。保育園にいくと給食の時間は修羅場のときやところがあるのだけどやっぱり「美味しさとは」とよく思ったな、そういえば。今年もたくさん「おいしー!」ってニコニコしたり、ほっぺぽんぽんってできたらいいね。
さて、昨日はNetflixで「令嬢アンナの真実」をみた。大掛かりな詐欺を次々と成功させてきたアンナと女性ジャーナリストの関わりを軸に、娘と父、出産を控える母親の仕事と夫婦と職場、赤ちゃんの時間と若者の時間など永遠のテーマをうまく盛り込んだ実話ベースの話だった。本物のアンナは放映権をNetflixに売り込んだ金でまたもや豪遊していたそうだから人間のそういう部分って変わらない。すごく面白かったし、「ラブ上等」に対するいろんなコメントのことも思い出してちょっと考えてしまったな。
さてアンナをみつつぼんやり“Key Ideas for a Contemporary Psychoanalysis Misrecognition and Recognition of the Unconscious” By Andre Green がどんな本だったかをチェックしていた。2023年12月にも読んでいた時期があったらしいが全く覚えていない。今回は原書のフランス語版にむけて書かれたペレルバーグの書評Jozef-Perelberg, R. (2005) Idées directrices pour une psychanalyse contemporaine d’André Green. Revue française de psychanalyse 69:1247-1261をみつけたのでそれも読みつつ目次を確かめつつ、今読むべきところを探ってみた。フロイトの「否定」論文は何度も読むべきものだけど、その「否定」では表せないだけでなく、精神分析実践ならではの心の動きを示すのがグリーンの「ネガティヴ」という概念だと思う。ネガティブはとらえどころがないからネガティブなのであってそれがwork(作業、仕事)できる心かどうかが精神分析プロセスを追うときの大切な指標になる。心とか主体とかあるんだかないんだかみたいなものを想定せざるをえないのはなんらかの動きを感じるということが起きたとき。ふと感じられる主体が現れるとき。時間が動くのとセット。それまで止まっていた時間が。「あれ?どうして今これ思い出したんだろう」「今ふと思い出しのだけど」と不思議そうに現れる気持ちは過去の出来事とつながっている。「あれなんで泣いているんだろう」とかも。過去は単なる時間ではないのだ。情動とくっついて時間として現れる、のでは?時間に関しては今年はベルクソンに加えてポール・リクールを読みましょう。積んであるからね。あとアガンベン。人は生きていること自体が行為になってしまうから色々難しい。さらに言葉も持ってるからややこしい。今年もそんなめんどくさい自分とつきあっていきまっしょい。
今年も、まずは今日、まずは朝起きるところから、と小さな時間を作ってがんばりましょか。どうぞよろしく。