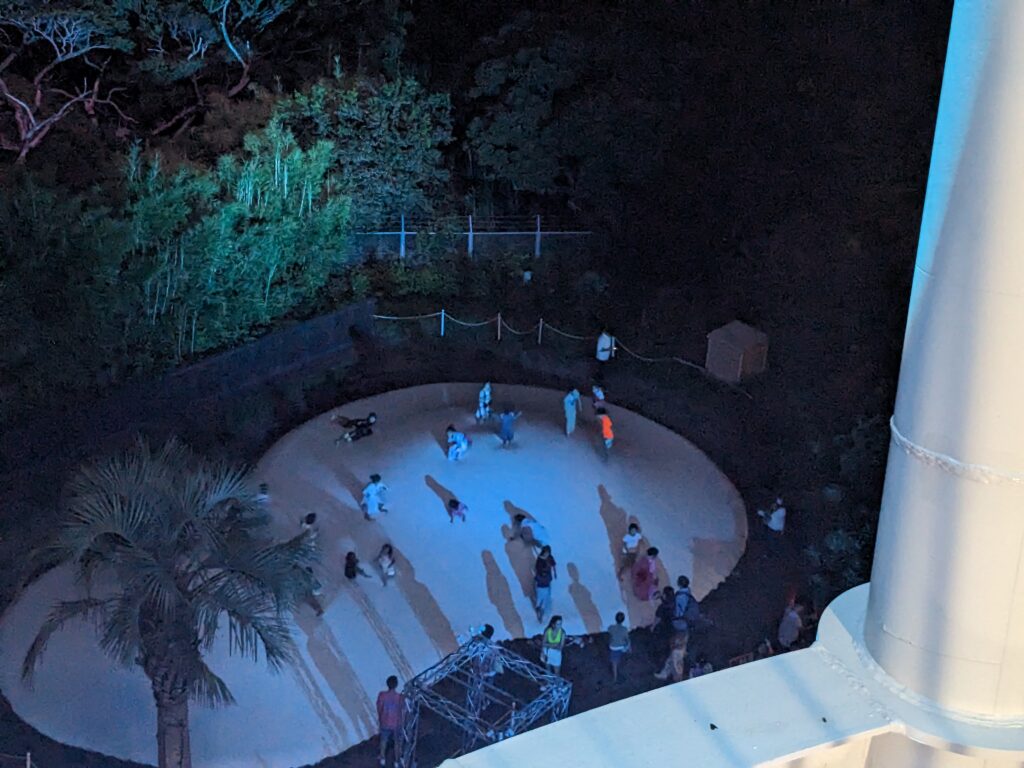COURRiER Japonのフロイトに関する記事の原文が読みたいな、と思っていたら山本貴光さんがくっつけてくれた記事を見つけた、と以前Twitterに書いた。そのメモをまとめておく。
ハアレツ紙(イスラエルの有力紙)に掲載された記事(英語版)はこれ。
Ofer Advert, “Angry Outbursts and Erotic Insinuation: What Freud Was Really Like”(2021.08.05)
https://haaretz.com/world-news/.premium.MAGAZINE-angry-outbursts-and-erotic-insinuation-what-freud-was-really-like-1.10089349
記者のOfer Aderetも取材されたReading Freud’s Patients Memoir, Narrative and the Analysandの著者アナト・ツール・マハレルもおそらくフロイトと同じくユダヤ人の歴史を共有していると思いつつKindleでこの本を読んだ。
この本に出てくるフロイトの患者たちはフロイトの伝記などにも登場するがこちらが読みやすいかも。
『フロイト : 視野の暗点』 Breger, Louis著,里文出版
患者の体験を通じてフロイトの精神分析実践を垣間見ることができる本で最近書かれたのがThe History of Psychoanalysis Series,のAnat Tzur MahalelのReading Freud’s PatientsMemoir, Narrative and the Analysand(Routledge, 2020)である。この本はWinner of the 2021 ABAPsa Book Prize Awardを獲得している。
それ以前だとBeate Lohser&Peter M. Newtonの”Unorthodox Freud The View from the Couch”しかなかったそうだ。高価な本だが試し読みができる。
https://www.guilford.com/books/Unorthodox-Freud/Lohser-Newton/9781572301283/reviews?utm_medium=social&utm_campaign=share-widget&utm_source=twitter.com
ちなみに『心の革命 精神分析の創造』(みすず書房)のジョージ・マカーリがこのLohser&Newtonの本のレビューをIPAジャーナル(1997)に書いているが、翌年には著者のPeter Newtonがこのレビューを a careless review だとして”Dear Sir,”で始まる文章を寄せていり。書いていることとやっていることが違うのでは問題、に対する読者の誤解に対する懸念、というか「ドイツ語でフロイトを読める私たちとしては」とストレイチー訳を批判しつつ書かれた手紙(?)は興味深い。
一方、Anat Tzur Mahalelは文芸批評の手法を取り、回想録の別の読み方を提供してくれル。
この本の「シリーズ編者による序文」はPeter L. Rudnytsky。フロイトが息子のように愛した精神分析家フェレンツィの『臨床日記』を重ねながらの紹介にしみじみした。https://www.msz.co.jp/book/detail/08695/
これまで患者の書き物は分析家のそれより周辺的な扱いを受けてきたがAnat Tzur Mahalelは患者の回想録を「精神分析文学」として文芸批評の対象とし、The author-analysandsたちを個別の患者というより「フロイトの患者」というグループとして扱う。
精神分析実践は、「メジャーな言語」に束縛されたマイノリティである自分が「ある言語の内において、その言語の外に出る」ことといえる。著者は序文でドゥルーズとガタリが見出した「マイナー文学」を引用し、フロイトの患者による回想録もそれとして理解することの意義を記す。
cf.1.叢書・ウニベルシタス 1068『カフカ マイナー文学のために〈新訳〉』 2.ジル・ドゥルーズ&フェリックス・ガタリ著, 宇野 邦一訳『ドゥルーズキーワード89』 堀 千晶&芳川 泰久(著) せりか書房
著者がドゥルーズ&ガタリ『カフカ マイナー文学のために』から引用するのはここ。
「穴を掘る犬のように、巣穴を作る鼠のように書くこと。そのために自分自身の未開の地点、自分自身の方言、自分だけの第三世界、自分だけの砂漠を見出すこと」
ー第3章「マイナー文学とは何か」33頁
引用はされていないけれどここも大事かと。
「マイナー文学の三つの特性とは、言語の脱領土化、個人的な事項がじかに政治的事項につながるということ、言表行為の集団的アレンジメントである。」
「偉大なもの、革命的なものは、ただマイナーなものだけである。」
ー第3章「マイナー文学とは何か」
アナト・ツール・マハレルの本では当然オグデンも登場する。聞くこと、書くこと、夢見ることについて考えるときには必ず引用される論文はこちら。邦訳も出ているはず。
Ogden, T. H.
“A Question of Voice in Poetry and Psychoanalysis.” Psychoanalytic Quarterly 67, 426–448. (1998).
The History of Psychoanalysis Seriesといえばこの本もそう。
『アタッチメントと親子関係 ーボウルビィの臨床セミナー』(金剛出版) ボウルビィ著 バッチガルッピ編 筒井亮太訳 のなかでボウルビィも言っている。
「患者の報告する実体験に敬意を払うこと、それがきわめて大切だと思います」
ミラノ・セミナーでの言葉だ。
Series EditorsはBrett KahrとPeter L. Rudnytsky。「シリーズ編者による序文」でブレット・カーも引用している箇所だ。
https://routledge.com/The-Milan-Seminar-Clinical-Applications-of-Attachment-Theory/Bowlby-Bacciagaluppi/p/book/9781780491677
https://kongoshuppan.co.jp/smp/book/b587826.html
さて、最初に登場するのはアメリカの精神科医、Joseph Wortis
02. Fragments of an Analysis with Freud by Joseph Wortis: Criticism and Longing
フロイトの被分析者の体験談の多くは1970年代にでている。しかしWortisは分析が終わって5年後、フロイトが亡くなって数ヶ月に早くも回想録を書いた。
この題名はもちろん「あるヒステリー分析の断片」(1905)=症例「ドーラ」と関連している。
患者が体験を早急に第三者に開きたくなるのには理由がある。端的にいえば、彼にとってフロイトとの分析がbad analysisだったからだろう。
しかしそれを「書く」行為が明らかにしたのは単に精神分析がもつ限界だけではなかった。常にongoing であること、著者は、この本であとから登場してくるH.D.の体験を素材に無時間性に関する学術論文も書いているが、そこでの議論とも通じるように思う。
ジョセフ・ウォルティスの『フロイト体験 ーある精神科医の分析の記録』(1989,岩崎学術出版社)は前田重治先生監訳。前田先生は東京で分析を受けていたときに古澤平作先生に本書を紹介されたと「解説」で書いている。
前田重治先生はご自身の体験も本にされているし、おすすめしたいご著書はたくさんあるけどきたやまおさむの歌を知っている人なら誰でも楽しめるのはこれかも。
→「良い加減に生きる 歌いながら考える深層心理』(2019, 講談社現代新書)著:きたやまおさむ&前田重治
前田重治先生の『「芸」に学ぶ心理面接法 初心者のための心覚え』(誠信書房)も。
ジョセフ・ウォルティス『フロイト体験 ーある精神科医の分析の記録』の次にminor textとして取り上げられるのはS.ブラントン『フロイトとの日々ー教育分析の記録』(日本教文社、馬場謙一訳)。
03. Diary of My Analysis with Sigmund Freud by Smiley Blanton: From a Deadlock of Silence to the Act of Writing
ブラントンの回顧録は妻のマーガレットにより編纂されたもの。この本をざっと読みながら元の回顧録や症例研究にあたるなかで精神分析体験に第三者が関わることのリスクについても考えさせられるだろう。ブラントンのこの本も前田先生の覚え書も目を逸らしつつ読む感じになってしまった。
ちなみに前も書いたがOgden,T.H.の関連論文と翻訳本もメモ。
“On Psychoanalytic Writing.” International Journal of Psychoanalysis 86, 15–29. (2005).
“Reading Harold Searles.” In Rediscovering Psychoanalysis: Thinking and Dreaming, Learning and Forgetting. London and New York, NY: Routledge, 133–153.(2009).
オグデンの著作で訳されているのは多分これらです。
2冊目『こころのマトリックス ー対象関係論との対話』4冊目『「あいだ」の空間 ー精神分析の第三主体』5冊目『もの思いと解釈』6冊目(かな?)『夢見の拓くところ』
Rediscovering Psychoanalysis Thinking and Dreaming, Learning and Forgetting→『精神分析の再発見 ー考えることと夢見ること 学ぶことと忘れること 』(藤山直樹監訳、 木立の文庫)
The New Library of Psychoanalysisのシリーズから新刊も出た。それについてはすでに書いた。
このシリーズはクライン派の本は結構訳されていると思う。独立学派は昨年でたハロルド・スチュワートと同じくスチュワートが書いた『バリント入門』。
以上メモ。関連の本を読んでいるのでこちらに付け足すかも。
資料作るの忘れてこんなことしてしまった。作ろう。