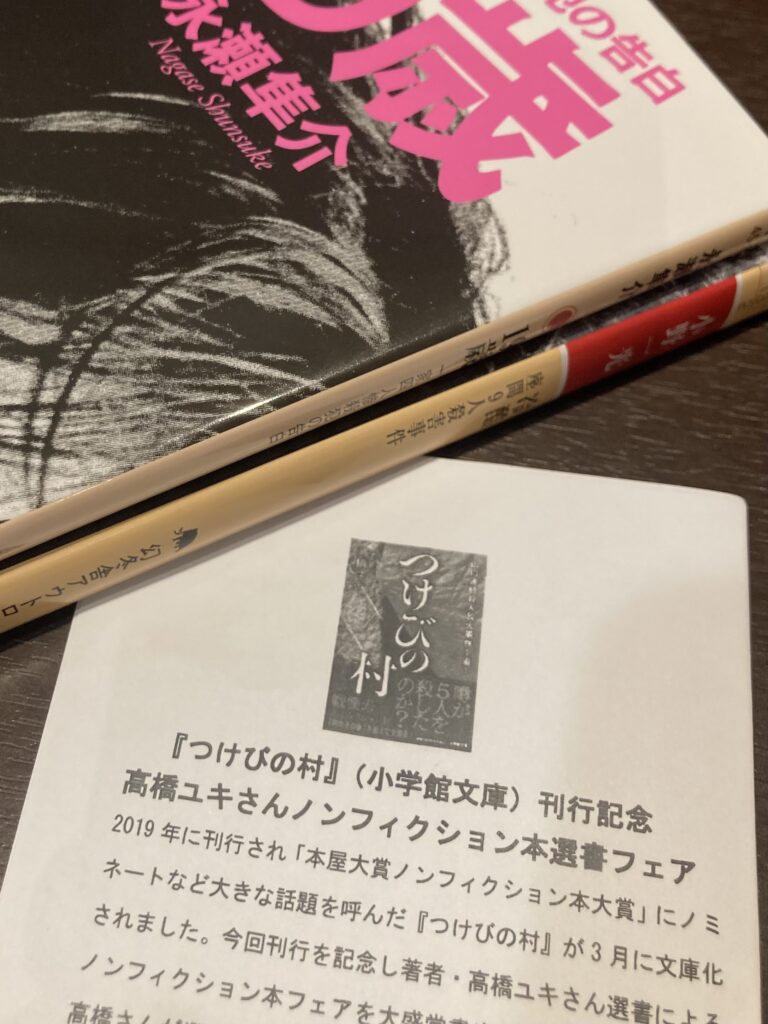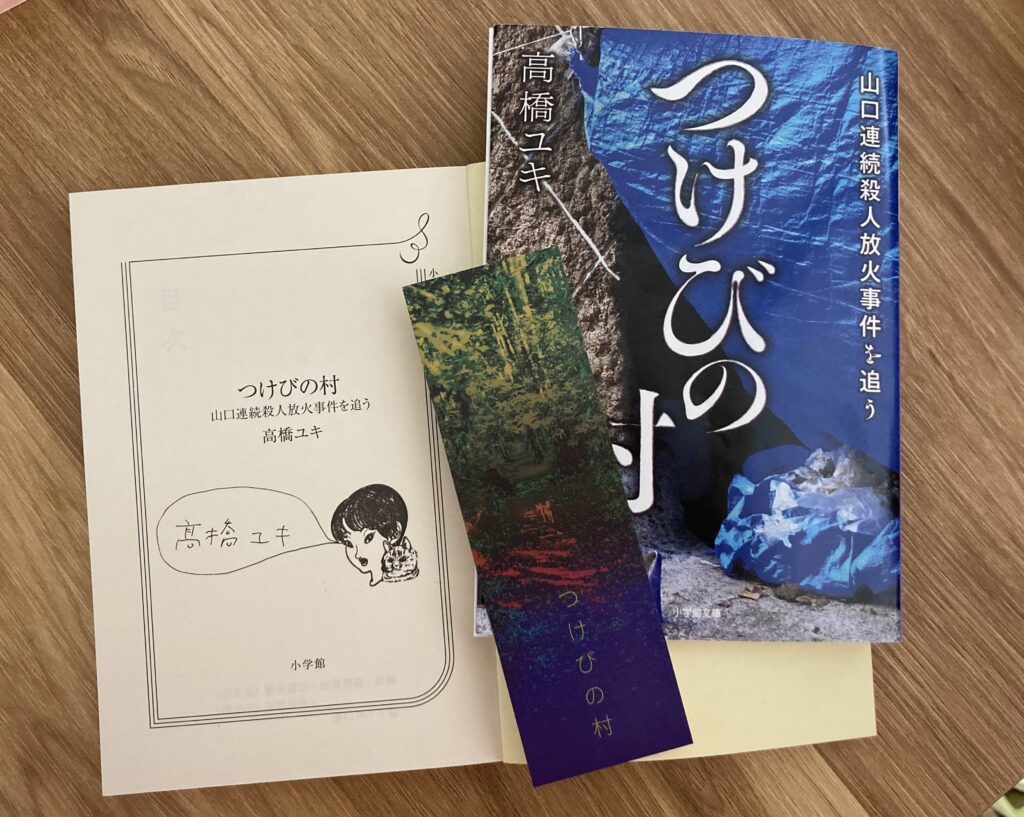昨晩から風が強い。今日は春の嵐とのこと。暖かいだけいいが雨も降るかもなのかな。レインコートを持っていこうかな。でもどこにあるんだっけ。
先日、代官山蔦屋書店で行われた「原爆、原発、風船爆弾――ハンフォードから福島へ/『スティーブ&ボニー』刊行記念 安東量子×竹内公太×山本貴光」というイベントの中で安東量子さんがハンフォードは最初から荒地だったわけではない。先住民などかつては人が住む土地だったのだ、というようなことを話していた。私が高橋ゆきさんのノンフィクションを好きなのも扱われる事件がその土地と大きく関係しているからだが、その土地の歴史を知ることはそこで生じた出来事の見方を変えるように思う。昨日のブログでも土地の名前を並べ立てた。
ウィキペディアでは「ハンフォード・サイト」はこう説明されている。
‘‘ハンフォード・サイト(the Hanford Site)はアメリカ合衆国ワシントン州東南部にある核施設群で、原子爆弾を開発するマンハッタン計画においてプルトニウムの精製が行われた場所である。その後の冷戦期間にも精製作業は続けられた。現在は稼働していないが、一部の原子力専門家から「アメリカで最も有毒な場所」「(事故が)起きるのを待っている、地下のチェルノブイリ」と言われるほど、米国で最大級の放射性廃棄物問題を抱えており、除染作業が続けられている 。””
また「これまでの歴史」として
““ここはコロンビア川、スネーク川、ヤキマ川の合流点に当たり、伝統的にインディアンの諸種族が出会う地点であった。1860年代に、ヨーロッパ人・アメリカ人が入植を始め、リッチランドなどの町が作られた。””
と書かれている。そうなんだね。ここで作られた「ファットマン」がもたらした被害は数字にできる範囲では「死者約7万3,900人、負傷者約7万4,900人、被害面積6.7 km2、全焼全壊計約1万2,900棟」だという。これもウィキペディアから。
色々なことが思い浮かび繋がっていき暗澹たる気持ちになる。想像するとはそういうことなのだろうと思うし、この暗澹たる気持ちがどこからきているのか自分に問うことでせめてそれに持ち堪えるということが大切なように思う。
昨日読んでいた『RiCE』という雑誌でイタリアンのシェフが引用していたネイティブアメリカンが大事にしているという言葉を思い出す。
““土地のことは七世代先のことを考えよ””
その土地やそこで生きた人々や起きた出来事に対してどのくらいの過去や未来を想像できるだろうか。そうするなかで問い直される現在を自分はどう過ごしていくべきか、べきというのはないとしてしてもどうしていきたいか。すぐに忘れたり忘れられたりすることに「まただ」と感じながら想起される事柄を今度こそ大切にできるだろうか。自分のことも疑わしいが意識的に疑ったところで起きることは起きるだろう。疑うよりも立ち止まること。情報ばかりスピードが速い世界で自分なりに立ち止まること。今日も一日。春の嵐に足元とか傘とか取られてしまわないように気をつけて過ごしましょうね。