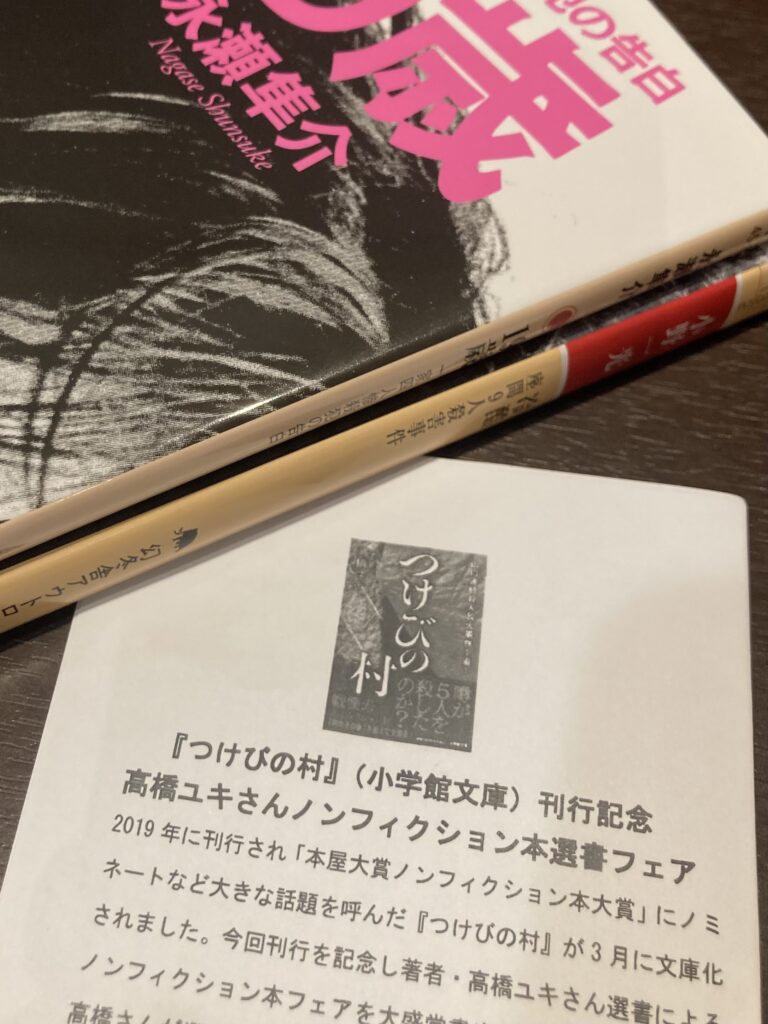二度寝、三度寝。コーヒー飲んでくしゃみがふたつ。雨はまだまだ降っている。どうしましょう。被害が広がりませんように。きっとこのあと何事もなかったかのように晴れるのでしょう。残酷。
『言語の本質』今井むつみ/秋田喜美 著❨中央公論新社❩を読んだ。精神分析における言葉の活用はいつも興味の中心なので言語学に関する本はそれなりに読んでいると思うが難しいのが多いから全然こなせていない。その点、この本は書き方も多分優れていて(私には優劣はわからない)引っかかりなく入ってきた。内容とは関係ないけど私はこの本を発達心理学の本だと思っていた。もちろん今井むつみさんはそれがご専門ということだし、言語は習得のプロセスと切り離せないわけだから発達心理学は常にその背景にあるわけだが、大学が発達心理学専攻で発達心理学の勉強が楽しくていまだに保育園でも仕事をしている私は「今は記号接地問題とかいう概念も扱うんだ。発達心理学もどんどん進化してるんだなあ」と思って嬉しく楽しく読んでいたのだ。なぜそんな発達心理学寄りの気持ちだったかといえば秋田喜美さんを秋田喜代美さんと間違っていたから。私は卒論で幼児に『赤ずきん』を読み聞かせてその感想を聞き取り分析するということをしたのだが参考文献のひとつが読書の心理学を研究されていた秋田喜代美さんの論文だった。今でもきちんと研究しておけばよかったなあと思うほど先行研究も現場(保育園)での調査も楽しかった。そんな誤解のもと『言語の本質』を読んでいて秋田さんはすっかり言語学の人になったのかと思いこみ、発達心理学の広がりに勝手にワクワクしていたわけだ。それはともかく毎日いろんな人の言葉を継続的に聞いているにも関わらず、というかその体験が増えれば増えるほどその人の言葉の習得や私が相手の言葉をキャッチする仕方などへの関心は深まるばかり。「そういう意味で使ってたのか」と聞き手だけでなく話し手自身が驚いてしまうような言葉の使い方使われ方も多いので話を聞く、聞いてもらう、というのは本を読むこととはまるで異なる体験ではある。生きている人を相手にするのだから当たり前だが。だからこそこういう専門的な本を読むことは大切。相手の言葉を大切にするためには忍耐と工夫と内省が必要。そのための支え。なんかすでにすごく売れているらしいのでみんなの基盤にもなってくれるかな。内容について全然書いてないけど「とりあえず読んでみて」というお勧めができてしまう本です。
はあ。雨やまないねえ。すでに被害がでている地域にこれ以上の被害が出ませんように。このあともたくさんのサポートを受け取れますように。どうぞお気をつけて。私たちも気をつけましょう。